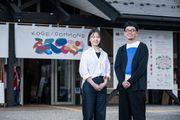「論理」が整えば、説得力が増す
明快で誤解のない日本語を使いこなすためにもうひとつ重要なポイントがあります。それが「論理」です。論理は、物事を的確に理解してもらうために、カテゴリーや性質の異なる情報を整理し筋道を整えることを指します。
一文一文は、正しい日本語で書かれているのに、全体を通して読むと意味が判然としない文章をひもとくと、構想段階で各文に含まれる内容が吟味されておらず、伝えるべき順序も間違っていることが大半です。
『当社は急成長している幼児教育市場に参入すべきだ』
こうした断定的な主張を通すためには、前提条件を示した上で正しい論理展開を行わねばなりません。もしそれを怠れば、結果ありきの独善的な主張と取られ、相手に悪い印象を残してしまうでしょう。
「導かれた結論に納得できない」「主張に一貫性が感じられず独りよがりに感じる」文章には、往々にして論理の飛躍、もしくは論理を構成する要素に欠落があるものです。
筋道が通った主張は議論を前に進めてくれますが、ただ言いたいことを並べただけの文章は、議論を発散させてしまいます。コミュニケーションやビジネスの停滞を招く危険因子と言っても差し支えないでしょう。
昔から「起承転結」や「5W1H」が、読みやすい文章の基本として引き合いに出されるのは、文章の骨格、つまり論理的な構成力が、読み手の理解に大きく影響するからなのです。
論理的な文章を書けるようになると、話し言葉においても説得力のある主張を展開できるようになります。相手に解釈や忖度を強いたり、疑問や不明点を解くためにカロリーを費やしたりする必要がなくなれば、課題の本質に向き合う時間を増やせるでしょう。
ビジネスパーソンの間でも知られるロジカルシンキングや、「顧客・市場(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3C分析、「Product(商品)」「価格(Price)」「販促(Promotion)」「流通(Place)」の4P分析に代表される思考のフレームワークは、正しい日本語を論理的に書けるようになってこそ役立つツールです。
論理を鍛えることによって、物事の因果関係がより一層明確になり、思考の精度も高まります。会議資料や提案書、議論の場であなたが発する言葉の説得力は格段に増すはずです。
人を動かす「コミュニケーション」の大切さ
端的で明快な文章を書いたり話したりできるようになると、周囲の反応が明らかに変わります。ビジネスパーソンとしての成長の手応えが実感できるようになるはずです。
しかし、ビジネスは多数の関係者とコミュニケーションを取りながら「合意」と「行動」を繰り返すことで成り立っています。
いくら内容が正しくても伝え方が間違っていたら、相手が拒否反応を示したり、聞く耳をもたなかったりすることがあります。コンサルタントもよくこのミスをしてしまいます。
明快で論理的な文章が一定の水準で書けるようになったら、次に取り組むべきは対人コミュニケーション力の強化です。
関係者が自分の果たすべき役割を正しく理解し、次のアクションを誘発できない働きかけは、どんなに精緻な論理で貫かれた主張も絵に描いた餅に過ぎません。
人を説得し動かすには、巧みな話術、言い回しを工夫するなどして相手の情動に訴えかける「レトリック(修辞学)」を身に付ける必要があります。
◎ レトリックの必要性
説得の目的は相手をこちらの思い通りに動かすことであり、そのためには論理を含むレトリックを総動員して、相手に「行動したい」と望ませることが必要である。
作成:アクセンチュア
古代ギリシアの哲学者アリストテレスが著した『弁論術』によると、人の気持ちに働きかけるレトリックには基本的な型があると言います。それこそが「エートス(信頼)」「ロゴス(論理)」「パトス(共感・感情)」からなる「三段論法」です。