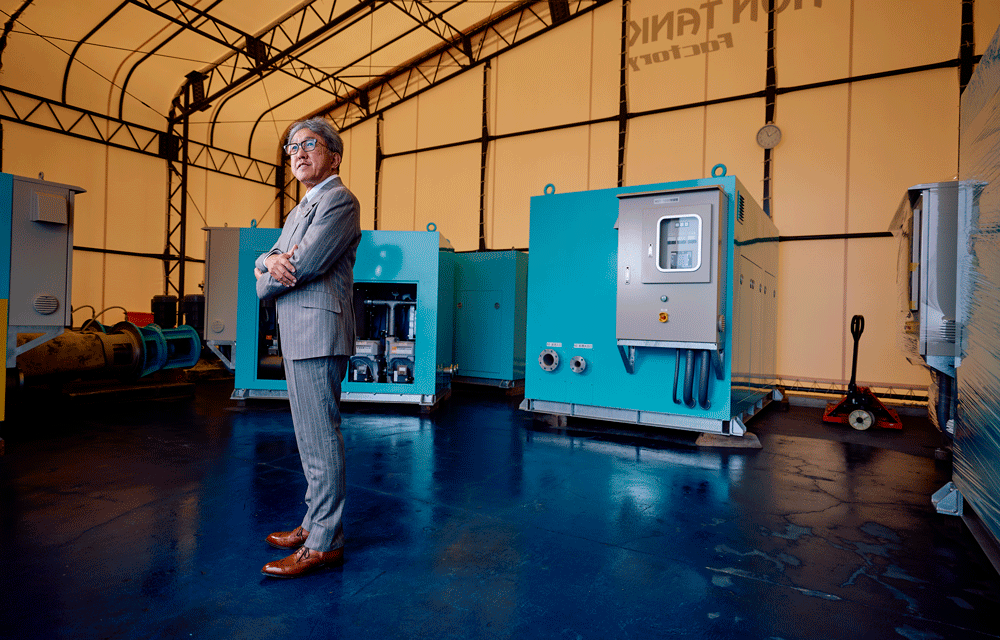古賀はアメリカに渡り、カリフォルニア大学バークレー校でMBAを取得する。そして、アメリカでならこの植物工場の高い技術を活かせるのではないかと考え、自ら起業を決意する。
「アメリカは、日本と比べ国土が広く、新鮮な作物が消費者に届くまでに時間がかかります。都市の近くに品質の高い植物工場をつくれば、確実に成功する。コンサル時代に学んだ日本の高い技術力を、この国でもう一度試してみたいと思いました」
機を同じくして、アメリカでも植物工場ブームが起きていた。度重なる天災によって起きた水不足、トランプ政権下で不法滞在者が摘発されたことで人件費が高騰、農業におけるコストが増加していた。
このままでは、コストはさらに上昇する一方だと、植物工場に注目が集まり、日本と比べて2桁多い額が一気にその市場へと流れた。これも古賀にとっては追い風となった。
高級イチゴがゴールではない
実は、古賀の会社以外の植物工場では、まだ技術的にレタスをつくることしかできない。レタスと比べ、複雑なライフサイクルを遂げる高品質なイチゴをつくっているのは、世界でも古賀のところだけだ。
古賀はコンサル時代の経験から、イチゴをつくるには技術的に何が足りないのかをよく理解していた。そこで、2年の月日をかけて、日本のありとあらゆる技術指導者を集めて研究開発を進め、美味しいイチゴをつくることに成功していたのだ。
植物工場を自分でつくると決めた古賀だったが、なぜ「イチゴ」にこだわったのか。他の作物で勝負をしなかったのはなぜか。それには大きく2つの理由があったという。古賀は語る。

写真=曽川拓哉
「1つは、ビジネス的観点で黒字化しやすかったからです。植物工場の業界を見ていて、いちばんの問題だと感じたのは、黒字化が非常に難しいという事でした」
食物工場でつくられるレタスは、味の差が出にくいうえに、簡単に出荷できることで価格競争が激しく、単価も安い。一方で、イチゴは日本では普段当たり前のように食べているから気づきにくいが、この品質のものは外国では存在しないレベルの高さだったという。
「そんな品質の商品を海外のマーケットに投下するだけで、付加価値の高いプロダクトになるのです。その希少価値から値段を通常よりも5倍高くしたとしても、需要があり、投資家からもお金が集めやすくなりました」
そして、もう1つの理由は、ブランディングのしやすさだったという。