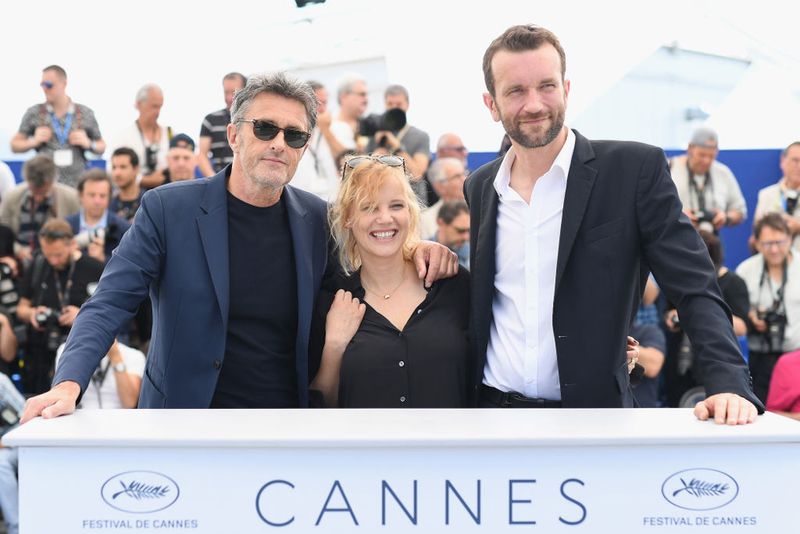ヴィクトル目線で見れば、ズーラは紛れもなく「ファム・ファタール」だ。いつも突然現れて、ふっといなくなる。そこだけ抽出すると、「運命の女に翻弄される芸術家の物語」に思えるかもしれない。
しかしズーラの方に焦点を当てると、彼女は男を振り回す小悪魔ではなく、単に自分の感情をごまかさない正直で純粋な女だとわかる。
たとえば恋人同士になった後、相手に嫌われそうなことを告白したズーラにヴィクトルが背を向けて去ろうとすると、悪態をつきながら突然驚くべき行動に出る。それは狙ったものではない。言葉にならない感情が高まって、思わずしてしまったのだ。
ズーラの中にあるのは、ヴィクトルと祖国の音楽への混じり気のない愛だけである。それはエピソードが積み重なるごとに明確になっていく。
まるで災厄のような恋
音楽舞踏団の初のワルシャワ公演の場面は楽しい。モノクロなのに鮮やかで賑やかな色彩が目に浮かぶ民族衣装、めくるめくダンス、そして「二つの心」の合唱の瑞々しいハーモニー。
しかし文化大臣からの「もっと政治的テーマを」「指導者礼賛の歌を」という圧力に団の管理部長カチマレクが従ったことから、民族音楽の固有性は薄められてしまう。一人の女性幹部は反発して退団するがヴィクトルは居残り、東ベルリン公演の後にズーラと二人、パリに亡命しようと考える。
この時待ち合わせに来なかった理由を、2年後のパリでの再会でズーラは言葉少なに語る。不安や恐れもあっただろうが、恋と芸術をまぜこぜにしないところに、ズーラの生真面目さが感じられる。
数年のインターバルの間に互いに恋人を作っていても、会えば相手こそがもっとも大切な人だと確認する、そんな切っても切れない関係になった二人。まるで災厄のような恋だが、これ以降、より積極的にそこに飛び込んでいくのはズーラの方だ。
そして1957年のパリ。クラブでジャズピアノを弾き、映画の音楽制作の仕事もするようになっていたヴィクトルの前に、ズーラは再び現れる。彼女が行動の自由を得るのに払ったプライベートな代償も、会話の中でさらりと明かされる。
セーヌ川を航行する船の上で身を寄せ合った二人の目線で、街のネオンや大聖堂がゆっくりと画面を流れていくシーンには、50年代、この街に集ったボヘミアンたちの哀愁が凝縮されているようだ。